芸人の舞台に欠かせない要素のひとつが「出囃子(でばやし)」です。
登場の瞬間に流れる音楽であり、観客に「これから何かが始まる」
という高揚感を与える大切な役割を担っています。
出囃子は単なるBGMではありません。
芸人のキャラクターや芸風を象徴するものであり、
観客にとっては「音を聴いただけで誰が出てくるかわかる」という強烈な記号になります。
落語の世界では江戸時代から三味線や太鼓が使われ、
現代の漫才やコントではポップスやロック、ヒップホップなど
多彩なジャンルが取り入れられるようになりました。
つまり、出囃子とは「音で伝える芸人の自己紹介」であり、
「舞台の第一声に先立つ最初の演出」なのです。
ツートライブの出囃子の特徴
若手コンビ・ツートライブの出囃子は、
ヒップホップやクラブミュージック系のインストゥルメンタルが中心だといわれています。
歌詞を排したビート主体の楽曲を選ぶことで、
言葉に頼らず観客のテンションを一気に引き上げるのが特徴です。
ファンの間では、
-
「USヒップホップっぽいインスト」
-
「重低音がガツンと効いていて痺れる」
-
「登場だけで会場の空気が変わる」
といった感想が多く聞かれます。
漫才のスタイルがテンポ重視のツートライブにとって、リズムで盛り上げる出囃子はまさに相性抜群。舞台に登場する瞬間から観客の身体を自然に揺らし、「このコンビは勢いがある!」と印象づける効果を持っています。
なぜヒップホップ/クラブ系を選ぶのか?
ツートライブが選んだ音楽ジャンルには、いくつかの狙いが見えてきます。
-
インパクトの即効性
ビートの効いた音楽は、一瞬で会場の空気を支配します。笑いが始まる前に観客の注意を集中させることができます。 -
漫才のリズムとの一致
彼らの漫才はテンポが速く、リズミカルに畳みかけるスタイル。ヒップホップのリズムと呼応することで、芸と音楽が一体化します。 -
若さ・現代性の表現
クラブ系やヒップホップは若い世代に馴染み深く、オシャレで都会的なイメージを演出します。芸人としてのブランディングにもつながります。
出囃子の歴史とお笑い文化
出囃子の歴史を振り返ると、その奥深さが見えてきます。
-
江戸時代の寄席文化
落語や講談の世界では、三味線や囃子方による生演奏が出囃子の始まり。演者を華やかに迎え、観客の気持ちを盛り上げる役割がありました。 -
昭和期の漫才ブーム
テレビ時代になると、漫才師はポップスや流行歌を取り入れるようになります。出囃子が芸人の知名度アップに直結するようになり、オリジナリティが重視され始めました。 -
現代のお笑いシーン
ジャンルはさらに多様化。ロックやヒップホップ、クラシックなどが登場し、芸人の個性を音楽で際立たせています。ツートライブもこの流れの中で、自分たちのカラーを強調する選曲をしているのです。
他芸人の出囃子との比較
芸人ごとに出囃子の選び方は異なり、それが芸風と深く結びついています。
-
ナイツ:昭和歌謡を思わせる軽快な曲。漫才の古典的スタイルと調和。
-
サンドウィッチマン:ポップで覚えやすい曲。親しみやすさを演出。
-
ミルクボーイ:明るくコミカルな曲調で、軽妙な掛け合いにリンク。
-
ダウンタウン:洋楽ロック系で、カリスマ性と勢いを強調。
-
千鳥:クセの強さを引き立てる、リズム感のある明るい曲。
この中でツートライブは「ヒップホップの重低音」という異色の選択をしており、
観客に強烈な個性を印象づけています。
音楽ジャンル別・出囃子の心理効果
音楽は観客心理に直接作用します。
ジャンルごとの効果を整理すると、ツートライブの選曲の意味がより理解できます。
-
ロック系:力強くエネルギッシュ、勢いのある芸風にマッチ。
-
ポップス系:親しみやすく、観客を安心させる。
-
ヒップホップ系:クールで都会的、スタイリッシュな印象を与える。
-
クラシック系:知的で落ち着いた雰囲気を醸し出す。
ツートライブがヒップホップを選んだのは、
まさに「勢い」と「スタイル」を両立させる狙いがあるからといえます。
出囃子と観客心理
心理学的に見ると、出囃子は「条件反射的な盛り上がり」を生み出す仕組みです。
観客は何度も同じ音楽を聴くうちに、「この音が流れる=笑いが始まる」という連想を持ちます。
これはパブロフの犬の実験に似た効果で、音楽が観客の心と身体を笑いに備えさせているのです。
さらに、重低音の効いたリズムは人間の鼓動とリンクしやすく、自然とテンションが高まります。
ツートライブの出囃子がファンに「痺れる!」と評されるのも、
音楽が生理的に盛り上がりを引き出しているからです。
海外コメディ文化との比較
日本のお笑いと海外のスタンドアップコメディを比べると、出囃子の扱いにも違いがあります。
-
アメリカ:スタンドアップコメディでは短いジングルやビートで登場。派手さよりもシンプルさ重視。
-
イギリス:トーク主体のため、出囃子は控えめで照明演出に重きを置く。
-
日本:音楽文化と寄席文化が融合し、出囃子が芸人のイメージ戦略の核になる。
ツートライブのように「音楽でまず空気を変える」手法は、
日本独自のスタイルといえるでしょう。
そのほかのまとめページはこちら
将来的な展望
今後、ツートライブがオリジナルの出囃子を持つ可能性も十分にあります。
吉本芸人の中には、ミュージシャンとコラボしてオリジナル曲を制作した例も多く、
音楽自体が芸人のブランドになるケースも増えています。
また、YouTubeやTikTokなどSNSでの発信においても、
オリジナル出囃子が「テーマ曲」として使われれば、ブランディング効果は絶大です。
AI音楽やサブスクサービスの普及により、オリジナル楽曲制作のハードルは下がっており、
ツートライブが今後そうした展開を見せることも大いに期待できます。
まとめ
ツートライブの出囃子は、単なる登場の音楽ではなく、芸風やキャラクターを象徴する
「舞台演出の核心」です。
ヒップホップやクラブミュージックの重低音は、観客を瞬時に舞台へ引き込み、
漫才の勢いをさらに加速させています。
ファンからも「かっこいい」「テンションが上がる」と評判で、
今後はオリジナル楽曲化など、さらなる進化が期待されます。
出囃子は芸人の世界観を音で伝える最初の一手。
ツートライブがこれからどんな音楽とともに舞台に立つのか、
その選択は彼らの芸人人生を彩る大切な要素となるでしょう。
参考・引用
-
吉本興業 公式サイト|所属芸人プロフィール
-
M-1グランプリ公式サイト「コンビ紹介」
-
日本大百科全書(ニッポニカ)「出囃子」解説|小学館デジタル大辞泉
-
日本音響学会誌「音楽が心理に与える影響」
-
北大路書房『音楽心理学入門』
-
BBC Comedy 公式ガイドライン https://www.bbc.co.uk/comedy
-
Duke University Press『Stand-up Comedy in Theory, or, Abjection in America』
-
各種スポーツ紙・芸能ニュース(劇場公演・出囃子に関する報道より)
-
Yahoo!ニュースコメント欄、SNS(X/Twitter)などのファンの声
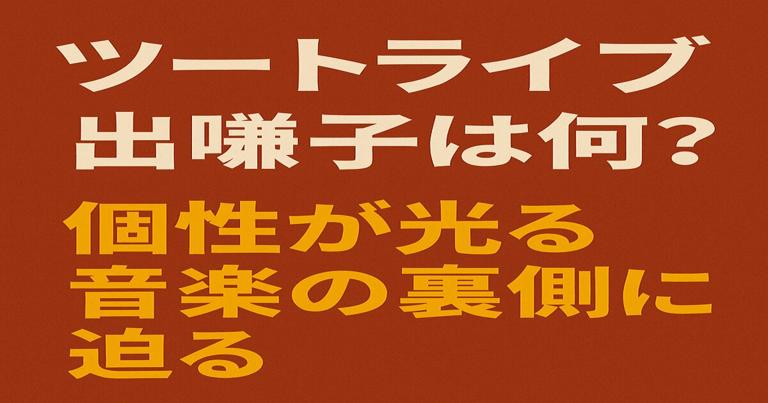
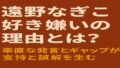
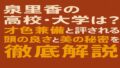
コメント